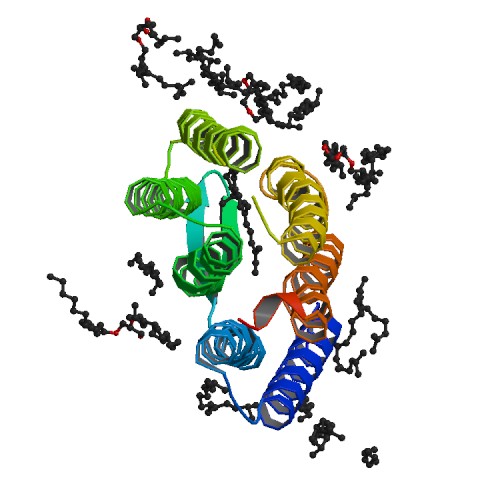計算化学・情報化学を活用した、物理化学の深化と現代社会の課題解決の研究をします。計算を活用した化学の新しい貢献分野を開拓します。多様な課題にチャレンジする意欲ある学生・共同研究者の参加を求めています。
- クラスター科学を基礎とした物質創成、化学反応理論、分子分光理論の進化
- マクロシミュレーションと連携したエネルギー問題への貢献(原子力研究開発機構受託研究)
- 分子クラスターから細胞に至る分子認識系の光励起ダイナミクスと素過程解明(科研費 特定A計画)
- 分子理論を基礎とした地球・惑星大気の精密物理化学研究分野開拓(科研費 基盤C)
- 核形成の学理と応用(豊田理研特別課題研究)
多様な研究課題に取り組めることは、コンピューターを道具とする計算化学の特徴です。また、一見無関係に見える課題の解決に必要なことが、実は共通していることもあります。量子化学をはじめとする分子シミュレーションが、実験や理論とならぶ研究手法として認知されてきましたが、現在もなお方法論的な研究の発展段階にあります。一方、個々の分子の性質から出発するのではなくて、大量の実験・観測データを網羅的に扱うことで自然を俯瞰的にとらえることにもコンピュターを活用できます。生命科学分野では、そのような研究が盛んです。問題に応じてアプローチの仕方を工夫しながら、ミクロとマクロを繋ぐ努力や、計算分子科学者だからできる異分野への貢献の努力をして行きます。
現実に解決すべき「実」課題の解決には、
- 問題の本質を注意深く検討し、必要な分子理論や計算手法を深化させること
- 物理化学の視点だけでなく、多角的に問題を検討すること
- 解析法を工夫して、計算結果の意味を明らかにし、発見につなげること
などが役立ちます。